Autographic 第十八話:生命
新井さんが鹿の腹を狩猟刀で切り裂くと、生臭さを纏った内臓がドロリと出てくるとともに大量の血が流れ出てくる。それをおじさんが、右側にいる猟犬たちと左側のロボの前に投げ置いた。
ロボと猟犬たちは内臓に食らいつき、尻尾を振りながら食べている。
(オェッ……)
強烈な臭いを嗅ぎ大量の血を見た僕は少し気分が悪くなったが、そんなこと気にしてられない。何か手伝おうと思い、おじさんに声をかけた。
「おじさん、何か手伝うことない?」
「おう、じゃあ鹿の脚を切り分けるからビニール袋に入れてくれ」
そう言うと、おじさんはリュックサックからビニール袋を取り出して地面に置き、鹿の後ろ脚を切り分け始めた。新井さんは手際よく前脚を解体しており、既に一本の脚をビニール袋に入れている。
僕はビニール袋を持っておじさんの横に立ち、切り分けた後ろ脚を受け取った。
「重いっ!」
おそらく十キロくらいあると思われる鹿の脚。右手で受け取った脚を落とさないように持ちながら、左手でビニール袋の口を広げる。脛の部分を持つ僕の右手には、まだ生温かい鹿の体温が伝わってきて、気持ち悪さを感じてしまった。
さっきまで目の前で生きていた鹿は死に、内臓は犬に食べられ体は切り刻まれている。流れる赤い血を見ながら生温かい鹿の体温を感じると、生きるために他者の命を奪わなければならないことを考えさせられてしまう。
「いただきます」
食事のとき誰でも言うこの言葉は、命をいただくから言うのかもしれない。
日常生活の中で肉を食べるのに残酷さを感じることはないが、それも他の人が命を屠っているからだ。命を奪わなければ生きていけないのに、それを他人に行わせて罪の意識を感じないようにしている社会が、なんだか動物が獲物を捕るより残酷に思われてならない。
自分たちが食べるために動物を家畜にし、システマティックに屠る。僕はいま、人間の残酷さを怖れながら、さっきまで生きるため必死にもがいていた鹿の生温かい命の欠片に触れ、つい先日まで病院のベッドの中で死んでしまうことを考えていた自分を恥じた。
自然の中で生きる動物たちは人間と違い、自分で他の命を屠り赤い血で身体を染めるが、残酷さや罪の意識を人任せにすることはない。なにより、人間のように命を大量生産して大量消費するようなことはせず、生きていくのに必要最低限の命しか殺さないじゃないか。
ビニール袋に入れた脚を地面に置き、おじさんからもう一本の後ろ脚を受け取ってビニール袋に入れていると、おじさんは新井さんと鹿の角を掴んで窪地に引きずっていった。
スコップで土をかけられて埋まっていく鹿を見ながら、ロボを連れ帰るより、野犬として一生を送らせたほうが幸せじゃないかと考えてしまう。このワイルドな犬は、鎖に繋がれ餌を与えられるより自然の中で暮らすのが合ってるんじゃないかと。
やがて鹿が土に埋まると、おじさんと新井さんがスコップを置き、鹿に向かって両手を合わせている。僕も鹿の脚が入ったビニール袋を地面に置き、二人と一緒に両手を合わせた。
鹿への祈りが終わって道具を片付けると、僕は鹿の前足が入ったビニール袋を渡された。猟犬を呼んで山を降りはじめたが、連れ帰るのは止めようと思っていたロボもついてくる。
追い払おうと思ったものの、ロボは猟犬たちとじゃれ合いながら僕らを追い越し、先に行ってしまった。





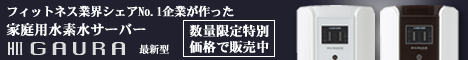

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!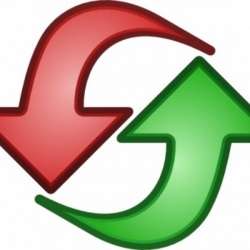 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品



 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone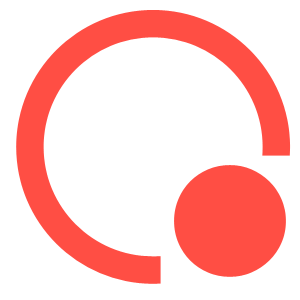




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません