夢幻の旅:第三十話
緩和ケア病棟は、今いる病棟の南側にある。
二つの病棟をつなぐ二階の連絡通路に行くため、俺たちはエレベーターに乗り込んだ。
扉が閉まると、俺は溢れ出る涙を袖口で拭き、大きく溜息をついた。
「なにがなんだか分からない……いったいどうなってるんだ……」
頭が混乱し、状況が把握できないままでいる。自分の体を蝕みはじめた癌も、蛍が死んだという三沢老人の話も、俺の心は受け入れることができない。
頭の中を整理する時間もないまま二階に到着し、エレベーターを降りた。
エレベーターホールから連絡通路へ向かい、二階建ての緩和ケア病棟まで歩いていく。
開放感のある大きな窓から射す明かりに、眩しさを感じながら歩く通路の途中、反対側からくる人と擦れ違うが、放射線治療を受けているのであろう、頭髪どころか眉毛まで無い男性、肌の色が土気色に変色している女性など、闘病の壮絶さを感じる人が多い。
今の俺の、錯乱と動揺が混在したような精神状態で癌治療に耐えられるのだろうか……。
連絡通路が終わって緩和ケア病棟に入ると、突き当りにナースステーションが見える。
横を歩いていた良美がナースステーションに行き、中にいる看護師に話しかけた。
「すいません、こちらに入院するよう言われた世良田光平ですが」
「はい、お部屋までご案内しますね」
中にいた看護師の一人が、ナースステーションから出てきて先頭に立って廊下を歩き、俺たちを病室まで連れて行く。
ナースステーションの前にある通路を右の方へ歩き、看護師はいちばん奥にある部屋のドアを開けた。
「病衣や必要なものは、中央病棟の売店で売ってます。今すぐ買いに行ってもかまいませんが、諏訪先生が治療について相談したいそうなので、三時には病室にいてください」
俺たちを病室に招き入れた看護師は、それだけ言うと軽く挨拶して出ていった。
手術ができない場所に腫瘍ができてるはずだが、どんな治療をするんだろう。よく聞く放射線治療や投薬治療なんだろうか。
不安な気持ちで癌治療について考えながらベッドに腰掛けると、まだ涙が止まらない良美の声が聞こえてきた。
「お義母さんたちに電話して、売店で病衣を買ってくる」
ハンカチで目頭を押さえながら、バッグを手に病室を出ていく良美。
その後ろ姿を見ながら、お袋やお義母さんに癌のことをなんて言うか考えあぐねた。
お袋もお義母さんも、俺が癌だと知ったら驚くに決まってる。お袋なんか、良美に俺の癌のことを話されたら、ずっと泣いたままになるに違いない。
膵臓癌ステージ四。お袋は、自分より先に死ぬかもしれない息子に、なんて声をかけるだろう。そして突然、死と向き合うことになった俺は、お袋やお義母さんになんて言ばいいのだろうか。
ベッドから立ち上がり、病室内をうろうろするものの、今の俺の精神状態ではなにも考えられない。
再びベッドに座り、この先どうすればいいのか思いを巡らす。癌のこと、良美のこと、そして蛍のことを……。
どれくらい時間が過ぎたのだろう。ベッドに座ったまま手を組み考え込んでいた俺の耳に、ドアが開く音が聞こえた。
「お義母さん、すごく動揺して泣いちゃってる。うちのお母さんもすぐ来るって」
「お袋、泣いてたか……」
当然だ。息子が余命三ヶ月と診断され、泣かない母親はいない。今は動転してるお袋たちに気丈に振る舞い、なるべく落胆させないようにすることだ。死の恐怖と闘う俺が、どれくらい空元気を出せるか分からないが。
良美が買ってきてくれた病衣に着替え、ベッドに横になって良美と話していると、程なくしてお袋とお義母さんが揃って現れた。
「光平……」
「光平君……」
涙が溢れ、言葉に詰まるお袋とお義母さんに、俺はベッドの中から声をかけた。
「癌らしいけど、まだ死ぬって決まった訳じゃないよ。五人に一人は治してるらしいし、俺も医者と、五人に一人を目指して治療するって約束したところさ」
そう言ったものの、お袋もお義母さんも涙が止まらず、言葉を発することもなかった。
二人を見ている俺のほうが辛くなり、なにも話せなくなってしまい、病室内には三人がすすり泣く音だけが響く。
なんとも言い難い状況に痺れを切らせ、良美に話しかけようとしたときである。
ドアをノックする音が聞こえ、諏訪医師が看護師を伴って病室に入ってきたので、反射的にベッドの上で上半身を起こした。
「世良田さん、看護師から聞いてると思いますが、治療方法についてお話しておきます」
「告知を受けたときは、手術が難しい場所にあるとのお話でしたが……」
諏訪医師は良美やお袋を見回してから、話しを続けた。
「ご家族の方ですか?」
「母と妻の母です」
「それならばいいでしょう。転移した悪性腫瘍を切除してからでは、膵臓の腫瘍を治療するのに体力が持たない。転移した腫瘍を含め、膵臓の腫瘍を中心に投薬と放射線治療をしましょう。放射線治療は明日からです」
諏訪医師の説明は明快だった。
頭の中で説明されたことを復唱していると、再び医師が口を開く
「ゲミシタビンという抗癌剤を中心に投与しますが、日本ではまだ承認されてない、アメリカで膵臓癌治療のために開発された新薬もあります。世良田さんさえよければ、新薬治験ということで使用します」
「先生、どんな薬でも治る可能性があるなら使ってください」
明日から治療じゃ考える時間もない。藁にもすがる覚悟で、どんな治療だろうが薬品だろうが使ってもらおう。
看護師に指示して病室を出ていく諏訪医師に挨拶し、俺は再びベッドに横になった。すると、お袋とお義母さんが良美と何事か話はじめ、三人で病室を出ていく。
なんだろうと思っていると、三人は病室に入ってきた。
「光平、私とお義母さんは入院に必要なものを買ってくるから」
「光平君、明日も二人で来るからね」
そう言うと、お袋とお義母さんはベソをかきながら俺の手を順番に握り、病室を後にした。
二人が出ていってから、新薬投与の同意書へ記入したり保険会社へ連絡したりと、やることが多くて大変だったが、夜遅くまで残っていた良美を見送り、その日は不安と死の恐怖に苛まれ眠れずじまい。
朝食後に医師からは薬品の効果と副作用の説明、看護師に放射線治療室へ連れて行かれて技師から説明を受け、前の晩から一睡もできず、ほとんど飯も喉を通らない俺の放射線治療がはじまった。
お袋とお義母さんも荷物を持って、朝から病室に来ている。
病室を出ていく俺の顔は不安そうだったのだろうか。三人とも涙を流しながら、放射線治療に向かう俺を見送ってくれた。
治療室のドアが閉まる音が聞こえ、大きな機械が横にあるベッドに仰向けに寝かされると、機械が動きはじめる。
当然といえば当然だが、放射線が体を通り抜ける感覚はない。
本当に、これで癌細胞が無くなるのか心配になってくるが、次の日も、また次の日も投薬と放射線治療が続く。
一週間、二週間と病院での癌治療が続いてくると、医師の説明どおりに髪の毛がごっそり抜けてくる。頭髪だけではなく、治療開始から三週間ほどで眉毛も睫毛も体中の毛は全て無くなった。
ツルツルの頭になった俺を心配してか、良美が帽子を被るように勧めてくるが、どうも帽子は苦手で被る気にならない。
ただ、睫毛がなくなったためか異常に目が乾くことを医師に話すと、諏訪医師は目薬を処方してくれた。
治療をしてるはずなのに次第に体のあちこちが痛むようになり、点滴の中に痛みを緩和する薬を入れてもらうが、頻繁に投薬すると体が慣れて効かなくなるので、なるべく我慢してくれと看護師は言う。
しかし、我慢できなくても投薬してもらえないときは、少しでも楽になるようにと良美が黒い日記を読んで俺の気を紛らわせてくれた。
入院生活とは退屈なもので、良美やお袋たちが来てないと話し相手もなく、やることもないので中央病棟のデイルームへ行ったり、ホスピスの一階にあるロビーで本を読んだりピアノの演奏を聴いたりする。
ホスピスのロビーでは、店の常連客の三沢さんと顔を合わせて癌であることを話し、悪性腫瘍の摘出手術が終わった三沢さんの退院を見送ったりして過ごす毎日。
そんな誰もいない退屈な時間ができたある日、ふと、自分で自分に送信していた最後のメールに本文が記載されていることを思い出し、体の痛みを堪えてベッドの上で起き上がり、スマホを見てみた。
『おとうさん』
本文にはそう書かれている。
俺が知らないうちに生まれ、知らないうちに去ってしまった蛍からのメッセージだろうか。
三沢さんから蛍が亡くなったことを聞いたものの、やはり心の片隅には、どこかで蛍は生きていると思う自分がいる。
ベッドから起き上がると痛む手を無理やり動かし、返信文を書いて送信した。
「おとうさんは、びょういんにいます」
自分で自分に宛てた返信。
バカバカしいと思いクスリと笑ってしまったが、こんなことでもしてなければ痛みに負けてしまいそうだ。
体の痛みどころか吐き気や目眩、貧血など、抗癌剤と放射線治療の副作用が日増しに強くなってきている。
このまま全身を癌に蝕まれ、激痛でのたうち回りながら死んでいく運命なのかもしれない。
でも、なぜかは分からないが、俺は自分が、何か大いなるものを待っているのを感じていた。
外を走る車の音や廊下で立ち話をする人の声が、時折り、僅かに聞こえてくる以外、自分の呼吸音しか聞こえないのではないかと思うような病室の静寂。窓のから射す、梅雨の合間の日差しを避けるようにベッドに仰向けになり、感覚を研ぎ澄ます。
俺は、徴を待っている……。





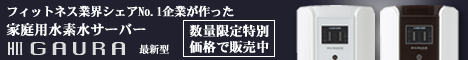

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!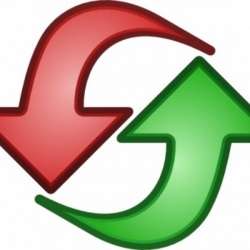 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品





 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone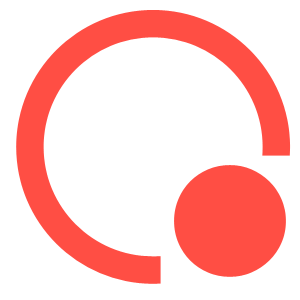



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません