夢幻の旅:第二十一話
――遠くから聞こえてくるサイレン。頭上に感じる人の気配。体に感じるのは冷たく硬い材質。
なぜか俺は寝ているようだが、動こうとしても体が言うことを聞かず、頭と右肩が痛い。
瞼を突き破って届く光を認識してゆっくり目を開け周りを見ると、どうも俺が寝ているのは売り場の床の上らしい。心配そうな表情で俺を見下ろす人がたくさんいた。
店のパートたちも、みんな集まって俺を見ている。
「俺、なんで寝てるんだ……?」
さっきまで仕事をしてたのに、なぜ床の上に寝てるのか訳が分からず、頭をもたげて起き上がろうとしたら、パートたちが慌てた様子で俺の体を押さえつけた。
「だめだめ! 動いちゃ!」
「突然倒れたんですよ! 寝ててください!」
凄い剣幕で捲し立てるパートたちに気圧され、もたげようとした頭を下すと近くでサイレンが鳴り止み、大勢の人間がドカドカ歩きながら近づいてくる。
来たのは三人の救急隊員たち。二人はストレッチャーを床に下ろし、一人は床に置いたバッグからペンライトを取り出すと俺の瞼を指で開き、光を当てて状態を確認しはじめた。
「倒れたのか……」
自分が救急車に乗せられようとしてるのに、まるで夢の中にいるようで実感が湧かない。声は遠くから聞こえてくるように感じるし、両目で見てる世界もグニャグニャ回転する。
「お名前言えますか」
救急隊員の問いかけにハッとし、条件反射的に答えた。
「世良田光平です」
「気分が悪いですか?」
「悪いです。耳鳴りもひどいです」
救急隊員は俺の顔の前に人差し指を突き立て、左右に動かしている。
何故そんなことをするのか分からないまま答えると、救急隊員はペンライトを胸のポケットに入れ、後ろに立つパートたちに向かって言った。
「重度の貧血をおこしてるようですね。危険な状態なので病院へ行きます」
救急隊員が俺をストレッチャーに乗せるため上半身と両足を持ったとき、ふと財布もスマホもロッカーに入れっぱなしだったことを思い出して、力が入らない体で気力を振り絞り声を上げた。
「ちょっと待ってくれ。私物を持っていきたい」
「分かりました。誰か取ってきてください」
こげ茶色のズボンのポケットからロッカーのカギを出して宮下に渡し、ついでに他の物も持ってくるよう頼んだ。
「さっきの忘れ物、たぶん俺の知り合いのだ。渡しとくから、一緒に持ってきてくれないか」
咄嗟についた嘘だった。見たときから気になる、黒い表紙の日記。
あんな子供が書いた日記、知り合いの物の訳がない。でも、なぜか俺から持ち主に届けなければならない気がしたのだった。
俺が見たページに書いてあった、お父さんが本を並べていたというのは自宅の本棚なんだろうか? でも、初めて子供に会うなら玄関で出迎えるはずだ。そう考えると、日記の持ち主が父親に会ったのは自宅ではないのかもしれない。
少しして、宮下が俺の私物を持って戻ってきた。
「財布とスマホ、それにこの黒い本でいいですか?」
「ああ、それでいい」
宮下から私物を受け取っていると、横からパートの高田が救急隊員と話してる声が聞こえてくる。
「どこの病院に運ぶんですか?」
「市立病院です。誰か付き添いで来られますか?」
「お店が営業中で行けないので……店長のご家族に連絡しておきます」
「お願いします。病院は受け入れ態勢を整えて待っているとのことなので、すぐ搬送します」
救急隊員がストレッチャーを持ち上げ、俺を救急車に運んでいく。車の後部ドアから救急車の中へ、ストレッチャーに寝たまま。
ドアが閉められると救急車はサイレンを鳴らし、ゆっくりと動きはじめた。
初めて乗る救急車。目が回る気分の悪さより好奇心が勝り、つい車内を観察してしまう。救急車には様々な装置や器具が設けられていてキョロキョロ見回していると、救急隊員が話しかけてきた。
「まだ気分は悪いですか?」
「目を閉じると意識が遠くなりそうな感じです」
「もうすぐ病院に到着します。頑張ってください」
救急隊員に励まされ、車内を見回すのを止めて天井を見ていると、救急車はサイレンを止めてスピードを落とし、どこかに停車した。
救急隊員が後部のドアを開けて、寝ている俺をストレッチャーごと運びだし、『救急搬入』と書かれた場所から病院に入っていく。
薄暗いその場所では看護師が数人待機していて、救急隊員と一緒に書類のようなものを確認しながら何ごとか話し、やがて看護師たちは用意していた病院のストレッチャーに俺を載せ替えられた。
救急搬入口から病院の奥に向かってまっすぐ進み、右手にある部屋に入るとストレッチャーから診察台に下ろされ、看護師にネクタイとワイシャツのボタンを外される。
待機してたらしい医師が俺の脈を取ったり聴診器を胸に当て、診察が終わってから看護師に何事か伝えると、看護師は点滴の準備を始め、俺はその場で点滴されることになった。
「世良田さ~ん。お体の具合がかなり悪いようなんで、何日か入院してもらいますよ~」
耳鳴りがひどく、まるで夢の中で話しかけられているような看護師の言葉に頷いてるうちに点滴の針を刺され、すぐに睡魔が襲ってきたかと思うと、看護師が出ていくのも気づかず眠りに落ちていった。





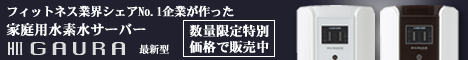

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!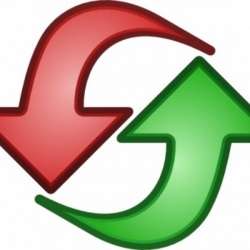 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品





 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone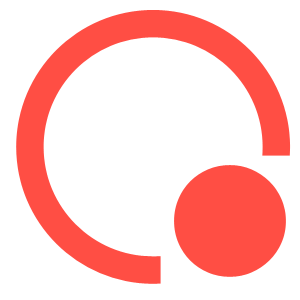




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません