The Wounds Are Never Healed 其の1
「せい!」
「どりゃあ~っ!」
寿司怒雷武で瀕死状態になりながら料理修行を開始したヘンタイロス同様、ベラマッチャも舐め犬店「ドッグファイト」で体力の限界を感じる毎日を過ごしていた。
同じ部屋に住むヒールの舐め犬、タイガー・ジェット・チンとキラー・トーア・オマタに誘われ、スモウ・レスラー出身の舐め犬同士で、毎朝、中庭に集まりスモウの稽古に励み体力作りに勤しんだのだ。
プロのスモウ・レスラーの激しい稽古に、小柄なベラマッチャは最初の頃はついていけなかったが、半年、一年と稽古するうち、彼らと互角にスパーリングできるようになっていった。
「打撃から入り、相手の重心を崩して投げ技に持ち込み、寝技で関節を極めるスタイルを確立したほうがいい」
小柄なベラマッチャのスモウを見たジャイアント・マラの助言で、ベラマッチャは大技に頼ることなく、地味だが、確実に相手を仕留めるスモウを身に付けていく。
小柄な自分の打撃が最大の効果を発揮する方法を考え、抜き手で相手の喉を点くことを思いつき、砂が入った鍋を火にかけて灼熱の砂を抜き手で突く修行を続け、身に付けた抜き手の突き技でキラー・トーア・オマタを失神させると、タイガー・ジェット・チンが、ベラマッチャの抜き手に「地獄突き」という名前を付けてくれた。
ハルク・コーガンやコカン・ハンセンのような舐め犬としての決め技も彼らの助言にヒントを得て、己の股間に地獄突きを応用したのだ。鋭く、早く、奥底までをも微妙な力で突く技を。
そのおかげで、ベラマッチャは死ぬことなく、ヒールの舐め犬として客をとることができている。
「よーし! そろそろ切り上げて控室に戻ろう!」
ジャイアント・マラの声で稽古は終わり、ベビーフェイスのスモウ・レスラーもヒールのスモウ・レスラーも車座になって中庭に座り、籠に山積みされた林檎を食べはじめた。
「おい、タイガー、昨日も額をカットしたのか?」
「あぁ……流血プレイが好きな客だったからな。このところ激しいプレイが好きな客が多くて疲れるぜ」
「生きていくためだ、辛抱しろよ。赤いのも白いのも出すのが俺たちの仕事さ」
コカン・ハンセンとタイガー・ジェット・チンの会話に、ドッと笑いが起こった。林檎が入った籠を回しながら、コカン・ハンセンが話を続ける。
「このところ、アブドーラ・ザ・ベラマッチャーも激しいプレイが続いてるじゃねえか。隣りの部屋でプレイしてても悲鳴が聞こえてくるが、贔屓の客でもできたのかい?」
「むぅ……三十代の若後家から、毎週のように指名が入るのだ。鞭で叩けば叩くほど、もっとぶってと声を上げる。最近では、体中を噛んだりせんと満足してくれん。僕も嫌気が差しはじめとるところだ」
「そいつは苦労するな! そら、疲れが吹っ飛ぶ林檎を食え! 嫌でも、舐め犬の掟を守らんと生きていけねえ」
ハルク・コーガンが差し出した林檎を手に取り、ベラマッチャは隣に座るジャイアント・マラに回した。ベラマッチャ同様、ジャイアント・マラも林檎を手に取り他のスモウ・レスラーに回していく。
なぜか苦みがある林檎は素晴らしく美味く、食べると頭がすっきりして疲れも癒される。だが、林檎を食わないと頭痛や吐き気が体を襲い、汗が滝のように流れ出し体が震えはじめるのだ。ひどいときには、幻覚や幻聴に苛まれることがある。それが林檎に原因があるのか、それとも舐め犬という特殊な職業に関係あるのか、ベラマッチャには判別できない。
「控室に戻って客を待とう。全員、起立! 舐め犬の掟を唱和!」
ジャイアント・マラの声で全員が立ち上がり、スモウ・レスラー出身の舐め犬仲間の掟を唱和しはじめた。掟の唱和は毎朝持ち回りで行い、今日はハルク・コーガンが当番である。
「第一の掟! 舐め犬のルールに従うこと!」
「第二の掟! 金持ちのママには親切にすること!」
「第三の掟! ストゥージとは話さないこと!」
「第四の掟! 清められたソーセージをしゃぶらせること!」
ハルク・コーガンに続いて舐め犬の掟を唱和したベラマッチャたちは、ヒールとベビーフェイスに分かれ、それぞれの控室に戻っていった。





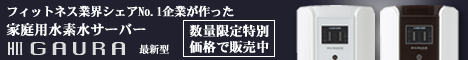


 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!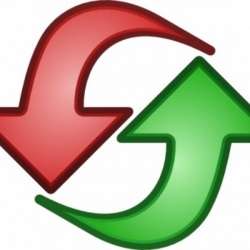 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品




 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone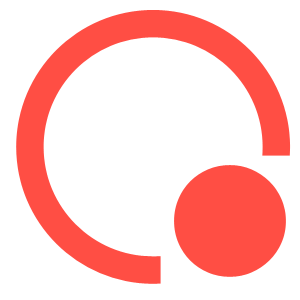




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません