夢幻の旅:第十六話
良美が家を出ていった事実を受け入れられず、俺は唇を歪めながら右手に持ったメモをクシャクシャに丸め、ゴミ箱めがけておもいっきり投げ捨てた。
病院にいたときから腹が鳴っており、体は食事を求めているものの心が受け付けてくれない。昨夜、食べずに残してある夕食が冷蔵庫に入っているが、食べずに自分の部屋へ行こう。メシは食いたくなったら食えばいい。冷蔵庫の中に入れてあれば、一日くらい置いといても大丈夫だろう。
自室へ向かい、窓を開けて枕元にスマホを置き、ベッドに寝転んだ。
良美の実家へ迎えに行こうか、それとも電話して、お義母さんと話をしようか考えるものの、どちらとも決めかねて時間だけが過ぎていく。
もうすぐ六月、気温はぐんぐん上昇し雨の日も多くなり湿度も上昇してきている。
額に汗をにじませながら窓の外に目をやると、晴れていた空は雲が多くなり、いまにも雨粒が落ちてきそうだった。
(とりあえず電話して、お義母さんと話してみるかなぁ……)
男は弱い生き物だ。家庭がうまくいかないだけで何も手につかなくなる。妻が出ていってしまうとなおさらだ。男がどれだけ女に依存してるのか、いまの自分が物語っている。
まずは良美と直接話そうと思い、スマホを手に取り電話してみるが、電源が切ってあるのかつながらない。仕方なく実家に電話しようとするものの、お義母さんになんて話すか言葉が見つからず、再び電話を枕元に置いた。
そりゃそうだろう、他の女との間に子供ができてましたなんて、どの面下げて義理の母に言うんだ? だけど俺も知らなかったんだし、このままじゃ蛍がかわいそうだ。
――なるようになる。
しばらく考えてからそう心の中で呟き、思い切って左手に持ったスマホの電話帳を開いて、良美の実家に電話をかけた。
「もしもし、光平ですけど……」
「あぁ、光平君」
電話に出たのは、お義母さんだった。
一瞬ドキリとして受話器を握る手に力が入ったものの、口内に湧き出す唾を飲み込んでから、ゆっくり話しはじめる。
「良美は帰ってますか?」
「今朝、大きな荷物を持って帰ってきたけど、部屋に籠ったまま出てこないのよ。夫婦喧嘩でもしたの?」
「まあ、そんなところです。携帯に電話しても良美が出てくれないんですけど、電話を代わってもえらえますか?」
お義母さんが受話器を手で塞ぎ、大声で良美を呼ぶ声が聞こえる。だが、お義母さんが何回も「良美、光平君から電話だよ」と呼んでも良美が電話の側に来る気配がしない。
「もしもし」
良美が電話に出ることを諦めたのか、電話からは再びお母さんの話し声が聞こえてきた。
「何回呼んでも部屋から出てこないから、夕飯のときに電話するよう言っとくよ。まったく、あの子もすぐ頭に血が上るんだから」
お義母さんの言葉に、俺の顔からは自然と笑みがこぼれた。
頭に血が上るのは親子そっくりだ。お義母さんだって、すぐ頭に血が上るタイプなんだから良美のことは言えない。
「分かりました。電話するよう伝えてください」
お義母さんに電話が欲しいことを良美に伝えてもらうことにして、俺は通話を終わらせた。





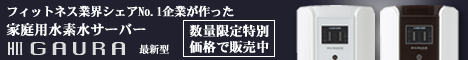

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!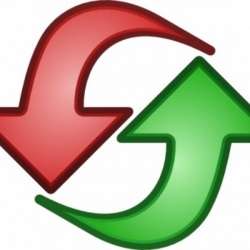 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品




 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone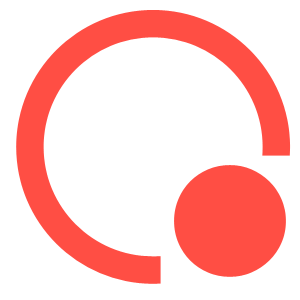




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません