夢幻の旅:第二十三話
――救急車の通過を知らせる、騒々しいアナウンス。
けたたましく鳴り響くサイレンに叩き起こされて目を開くと、カーテンで仕切られた病室のベッドの上で寝ていた。
(そうだ、店で倒れて入院させられたんだ……)
俺の眠りを覚ましたサイレンが近くで鳴り止んだということは、どうやら朝から急患が病院に運ばれてきたらしい。
ベッドサイドに置いてある腕時計を見れば、まだ朝の六時すぎ。ベッドに腰掛けて背伸びしながら自分の姿を見ると、ワイシャツも着てなくベルトも無い、スラックスに肌着、なぜか靴下を履いたままの姿である。
昨夜は良美とお袋、お義母さんが来た。家を出ていった良美は実家でお義母さんに諭され、蛍に会ってみる気になりはじめたようだったが……。
病室を漂う料理の匂いに腹が刺激されるせいなのか、昨日の嫌な夢が脳裏をかすめる。まずは良美と話し合ってみないことには始まらない。今日、着替えを持ってくると言ってたし、その時にでも少し話をしてみよう。
点滴に睡眠薬でも入っているのか、目が覚めても頭がすっきりしない。それでも眠る気にならず、朝食までの時間をニュースでも見て暇を潰そうと腕時計の横にあるスマホに手を伸ばしたとき、もうひとつ黒い物が置かれているのが見えた。
「忘れ物の日記、持ってきたんだっけ」
児童書の棚に置いてあった、黒い表紙の日記。
どういう訳か気になり、忘れ物として処理しようとしたところを、救急車に運ばれる直前、私物と一緒に持ってきてもらったのだった。
ベッドに入ったまま状態だけ起こし、日記を取ってページを開くと、やはり子供の字で日記のような内容が記されている。
『三月二十五日 お父さんにあいにいきました。お父さんはおみせの人とおはなしをしていました』
昨日見たページでは初めてお父さんと会ったと書いてあったが、次に会ったときは、お父さんは店の人と話をしていると書かれていた。前のページで本を並べていたことといい、お父さんは俺と同じく本屋で働いているのかもしれない。
そう思いながらページをめくった。
『四月七日 お父さんのおみせにいきました。きょうはおじいちゃんのおたんじょうびなので、お父さんのなまえはおじいちゃんがつけたおはなしをしました』
(――蛍か?)
心臓が止まるような衝撃が俺の体を貫いた。
四月七日、親父の誕生日に蛍と初めて話したのを覚えている。あの日、確かに蛍は、俺の名前を名付けたのは親父だと話していた。でも、親父は十二年前に癌で死んでるし、明子だって蛍を産んですぐに亡くなったんじゃないのか。
いったい、誰が蛍に、親父の誕生日や俺の名付け親が親父だと教えたんだ……。
あの時、蛍が俺のことを知っているのに驚きながらも、それが当然のような感覚で聞いていたし、二度目に会ったときは川の畔を歩きながら、蛍が俺のことを知っているのは当たり前のことと感じていた。
それは血のつながった親子だからこその感覚かもしれないが、考えてみれば、蛍が俺のことに詳しいのは理解しがたいものがある。
日記を閉じてベッドサイドのテーブルの上に置き、両手で顔を覆い考え込んでいると女の声で名前を呼ばれ、ベッドを仕切っているカーテンが開いた。
「世良田さん。朝食を取りに来てください」
時間は朝七時。白衣を着た中年女性に呼ばれ、点滴が付いたイルリガートルを押しながら後をついて病室を出ると、廊下に銀色の大きなワゴンが置かれていて、入院患者が自分の名前が書かれた朝食を持って病室へ戻っていく。
俺もワゴンから自分の名前が書かれたプレートを探し出し、病室に戻った。
今になって分かったが病室は四人部屋、俺以外の三人は老人である。病室内を見回した後、オーバーテーブルに朝食を乗せ、ベッドに入って食べはじめた。
朝食は、ご飯に味噌汁、肉団子のあんかけ、ほうれん草のしそドレッシング和え、それにプロセスチーズが付いている。
昔と違い、最近は病院食も美味そうになったものだ。子供の頃、友達が交通事故に遭って入院し、お見舞いに行ったときに見た食事は、匂いだけで食欲が失せたものだが。
晩飯を食っておらず腹が減っていたためか、すぐ食い終わってしまい、ワゴンにプレートを戻しベッドへ戻った。
再び黒い表紙の日記を取り、ページをめくって読みはじめる。
『四月十日 お父さんと川のよこでおはなししました。わたしがいったら、お父さんはうれしそうなかおをしました』
――蛍と二度目に会った日だ。
この日、初めて店の横にある川の畔を歩きながら話をした。これは間違いなく蛍の日記だ。でも、なぜ子供のように平仮名ばかりで書かれている? 蛍が俺と明子の子供なら、もう二十六歳のはずだ。こんな子供のような字を書くはずがない。やはり誰かが、何か目的があって俺をだまそうとしているのだろうか……。
日記を閉じ、ベッドに横になりながら考えていると看護師が病室に入ってきた。
「点滴を交換します」
昨夜から点滴をされたままで、針が刺さったままの左腕に鈍痛が続いている。痛みに苛立ちながら点滴の交換を見ていると、看護師は慣れた手つきで交換してしまい、病室から出ていく。
いつまで入院するのか看護師に尋ねようとしたとき、入れ替わるようにして病室に良美が入ってきた。
「あなた、着替え持ってきたわよ」
大きなバッグを肩から下げて現れた良美に、俺の顔は自然と綻んだ。
「朝早くから悪いな」
「なに言ってるのよ。倒れた人は余計な気を使わなくてもいいの」
そう言って、良美はバッグから取り出した衣類を備え付けのクローゼットにしまい込んでいく。それを見ていると、なんだか日常生活が戻ってきたようでホッとする。
「なあ、俺はどれくらい入院するんだろうな」
「さっき婦長さんに聞いたんだけど、午前中に診察してから決めるみたい」
「精密検査の結果も気になるし、大したことがなければいいんだけどな」
少し前、家の近くの病院で検査したばかりだ。仕事もあるし、長期間の入院は避けたいところだ。偶然にも今日は公休日だが、明日は早番で出勤。明日以降も入院するなら、今日中に連絡して店舗のシフトを変更しなければならない。
俺はベッドに寝たまま、医師の診察を待つことにした。





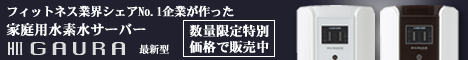

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!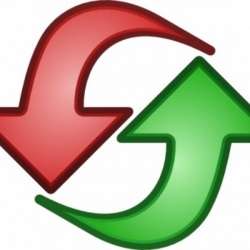 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品






 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone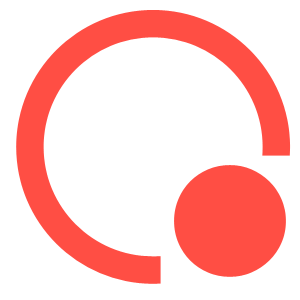



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません