夢幻の旅:第二十二話
「良美! 脚立に上ってくれ!」
一階の屋根に付いている雨樋を外し終えた俺は、季節外れの大雪で壊れた家の雨樋を修理するため、良美に手伝ってもらって新しい雨樋に交換しようとしていた。屋根に付いていた雨樋は雪の重さに耐えられずに破壊され、一階の屋根の真ん中あたりで半分が砕け落ちてしまったのだ。
ホームセンターで買ってきた雨樋を、脚立に乗った良美に下から支えてもらっている間に、もうひとつの脚立に乗った俺が取り付けてしまう段取りである。
まだ寒い春の青空の下、風に吹かれながら縦に伸びる雨樋にパーツをはめ込み、インパクトドライバーを使って屋根にネジ止めしていると、下から支えていた良美の大声が聞こえてきた。
「あなた! まだ終わらないの!」
良美の両腕に限界がきたらしい。急いで両端をネジ止めし、良美に声をかけた。
「もうだいじょうぶ! 放していいよ!」
「やだぁ、運動不足かしら? 腕がプルプル振るえちゃって」
良美は脚立を降り、横で見ていた蛍と話している。庭のベンチに移動し、蛍が淹れたお茶を飲みながら談笑する二人を見ていると、自然と俺の心も和む。
「お父さんがモタモタしてるのが悪いんです。良美さん、五分くらい両腕を上げたままでしたよ」
「あの人、考えながら行動するのが苦手だから、蛍ちゃんがやってたら怒ってたかもね」
「私なら怒鳴ってますよ。我慢して夫を支える良美さんは偉い!」
悪口を言いながら笑う二人に心の中で文句を言うものの、自分の顔は笑っているのが分かる。何気ない日常の中の、ごく普通の家族の風景。その当たり前のことが、なんと幸福に感じることか。
――蛍を引き取ってから、もうすぐ一年になる。
初めはぎこちなかった良美と蛍も、最近は本当の親子のように仲がいい。一緒に買い物へ行き、料理も二人で作ることが増えた。良美は娘に料理を教え、蛍はファッション雑誌を見ながら、流行の服について良美と話したりしている。
蛍を引き取るため、なんとか良美の理解を得ようと努力していた時期を、昨日のことのように思い出す。
初めて蛍のことを打ち明けた日、良美は怒って部屋に籠り、精密検査から帰ってきたら実家に帰ってしまっていた。お義母さんに電話したものの良美は電話に出ず、しばらく一人で過ごした。
なんとか良美を説得したものの、今度はお義母さんが怒ってしまい、俺と良美とお義母さんの三人で話し合いをしたのも懐かしい。
うちのお袋は、いきなり孫ができたことに驚いていたが、喜んで毎日のように蛍に会いに来てた。
そんなことを思い出しながら雨樋の修理を終え、インパクトドライバーを片付けて庭に出ると、良美と蛍が手招きして俺を呼んでいる。
「お父さん!」
「あなた!」
近づくと、二人は降り注ぐ陽光を浴びて光る、ベンチの上に置いた位牌に向かい、庭に跪いて目を瞑り手を合わせていた。
「誰が死んだんだ?」
不思議に思って聞くと、二人はケラケラ笑いながら振り返った。
「やだ、あなたが死んだんじゃない」
「お父さん、自分の戒名が分からないんだ」
意味不明なことを言いながら笑う二人を見て驚いていると、突然、良美と蛍が頭のてっぺんから溶けだし、次第に消えていく。
「うわあぁ~っ! 良美! 蛍!」
まるで、真夏の太陽を浴びたソフトクリームが熱を吸収してドロドロになるように、頭から溶ける良美と蛍。溶解し、ベンチの上に溜まっていく二人を狼狽えながら両手で搔き集めるが、指の隙間をすり抜けてしまい、どんどん土の上に流れ落ちる。
民家の庭で二人の人間が溶けてるというのに、家の前を歩く人たちは俺を指さし笑って通り過ぎていく。
「お父さんは死んじゃったんだよ!」
ベンチの上に残る、蛍だった液体から聞こえてくる声にビクンと体を震わせ、気が付けばベッドの上に寝ている俺がいた。
(夢だったのか……)
目の前には煌々と灯る照明。白い天井が視界いっぱいに広がっている。
妙な夢を見たと思いつつ、天井を見つめたまま目を瞬かせていると、人の気配を感じて顔を左に向けた。
「あなた……」
「良美……」
横には、椅子に座った良美がいた。お袋も、お義母さんも。
「お店から電話があって、倒れたって聞いて慌てて来たのよ」
――そうか。俺は店で倒れ、病院に運ばれたんだ。救急車で運ばれ、診察室で点滴をされるところで記憶が途切れているが、病室の不必要なまでに明るい光に曝され、急激に記憶が甦ってくる。
「お店の人たちも、心配してお見舞いに来てくれたんだから。今日はゆっくり休んで」
「まったく心配させないでよね。もう遅いから私たちは帰るよ」
「光平君、良美にはよく言っといたから二人で話し合って」
ちょっと怒り気味のお袋と、ホッとした顔のお義母さん。二人は良美と少し雑談してから病室を出ていったが、残された良美との間に気まずい空気が流れ、なかなか話しだせない。
それも当然か……。良美が家を出ていったのは蛍のことだ。亭主が過去に子供を作ってたなんて知ったら、どんな女でも嫌気が差すだろう。
病室に長い沈黙が続き、耐えられず良美に話しかけようとしたら、良美から口を開いた。
「お母さんに言われちゃった……」
「何を?」
「光平君も知らなかった子だし、生まれたのを知ってたら、子供を捨てて他の女と結婚するような人じゃないって」
お義母さんらしい、ストレートな言葉だった。たしかに蛍が生まれたことを知ってたら、俺は蛍を引き取り一生独身でいただろう。きっと良美と出会っても、恋に落ちることはなかったに違いない。
命には限りがある。自分の分身である子供に命を受け継いでもらい、その子もまた次の世代に命を繋げることを生物は営々と繰り返してきた。自分の子供を放っておいて我が身の幸せを求めるなんて、俺には考えられない生き方だ。
そんなことを考えていると、良美が言葉を続けた。
「私たちには子供がいないんだし、天から授かったと思って会ってみればって。やっと父親に会えた子を邪険にしちゃあいけないよって言われたの」
お義母さんの言葉の有難さに、ベッドに寝ている俺の目から涙が溢れ出てくる。話している良美も涙ぐんでいるようだ。
天井を見つめたまま涙も拭かず声を出そうとしたとき、ハンカチで目頭を押さえながら良美が立ち上がった。
「もう遅いから今日は帰る。明日、着替えを持ってくるから」
「あぁ……頼む」
バッグを持ち、電気を消して病室を出ていく良美。
ドアが閉まると爆発しそうな感情を堪えきれなくなり、シーツを頭までかけ声を押し殺して泣いた。





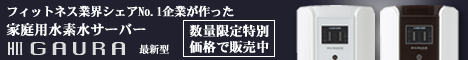

 ブロトピ:Twitterで拡散し合う部
ブロトピ:Twitterで拡散し合う部 ブロトピ:ブログ更新しました!
ブロトピ:ブログ更新しました!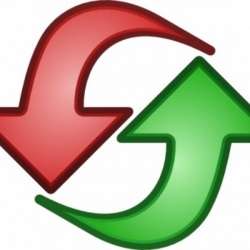 ブロトピ:今日のブログ更新
ブロトピ:今日のブログ更新 ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』
ブロトピ:アクセスアップ専用のアンテナサイト『Reviewers(レビュアーズ)』 ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ!
ブロトピ:ブログ更新通知をどうぞ! ブロトピ:本のおすすめ
ブロトピ:本のおすすめ ブロトピ:作品
ブロトピ:作品




 Inazuma Ramone
Inazuma Ramone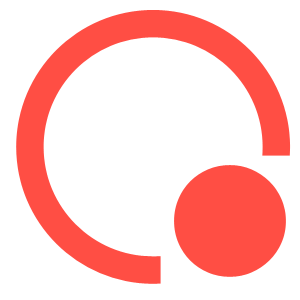



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません